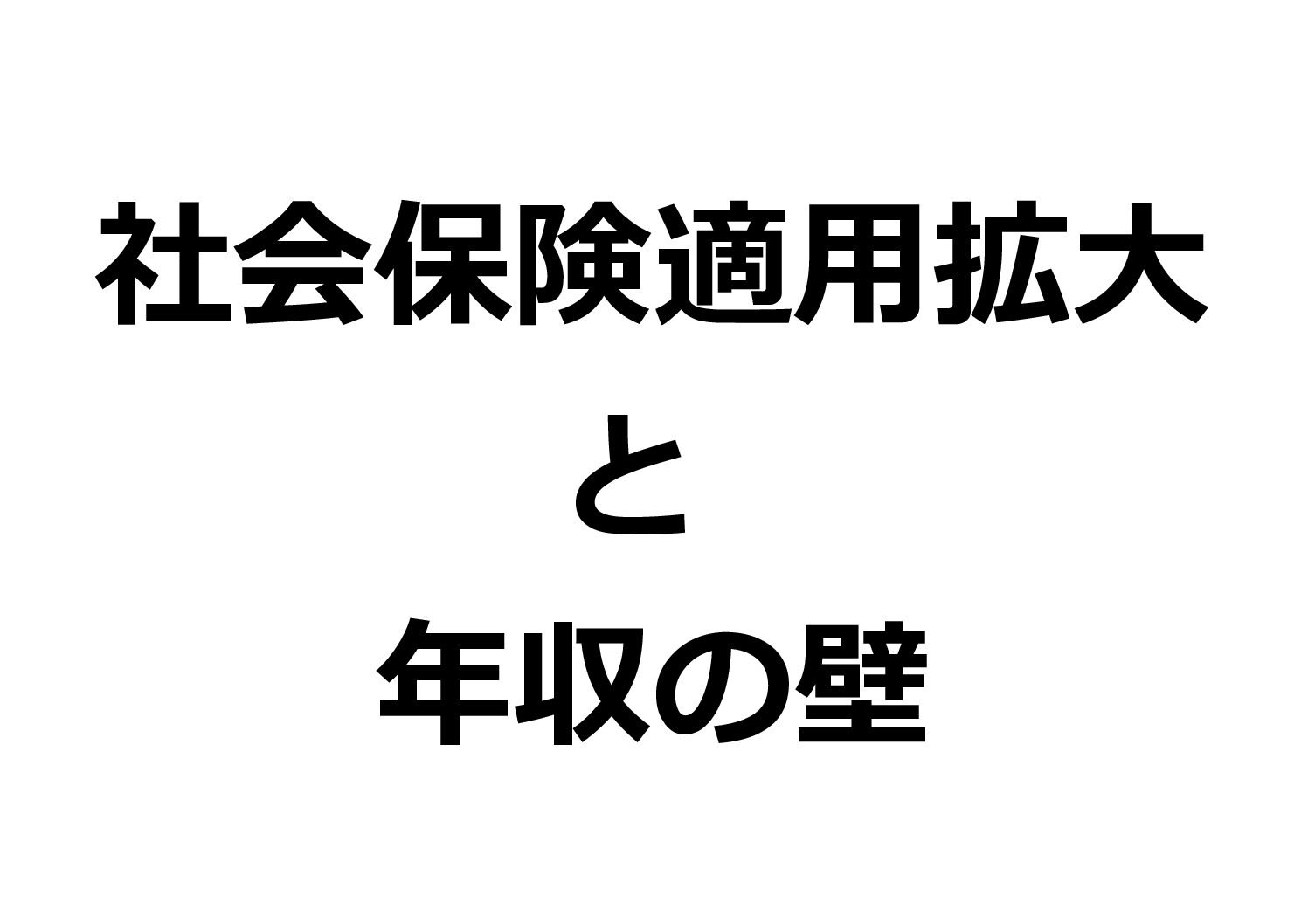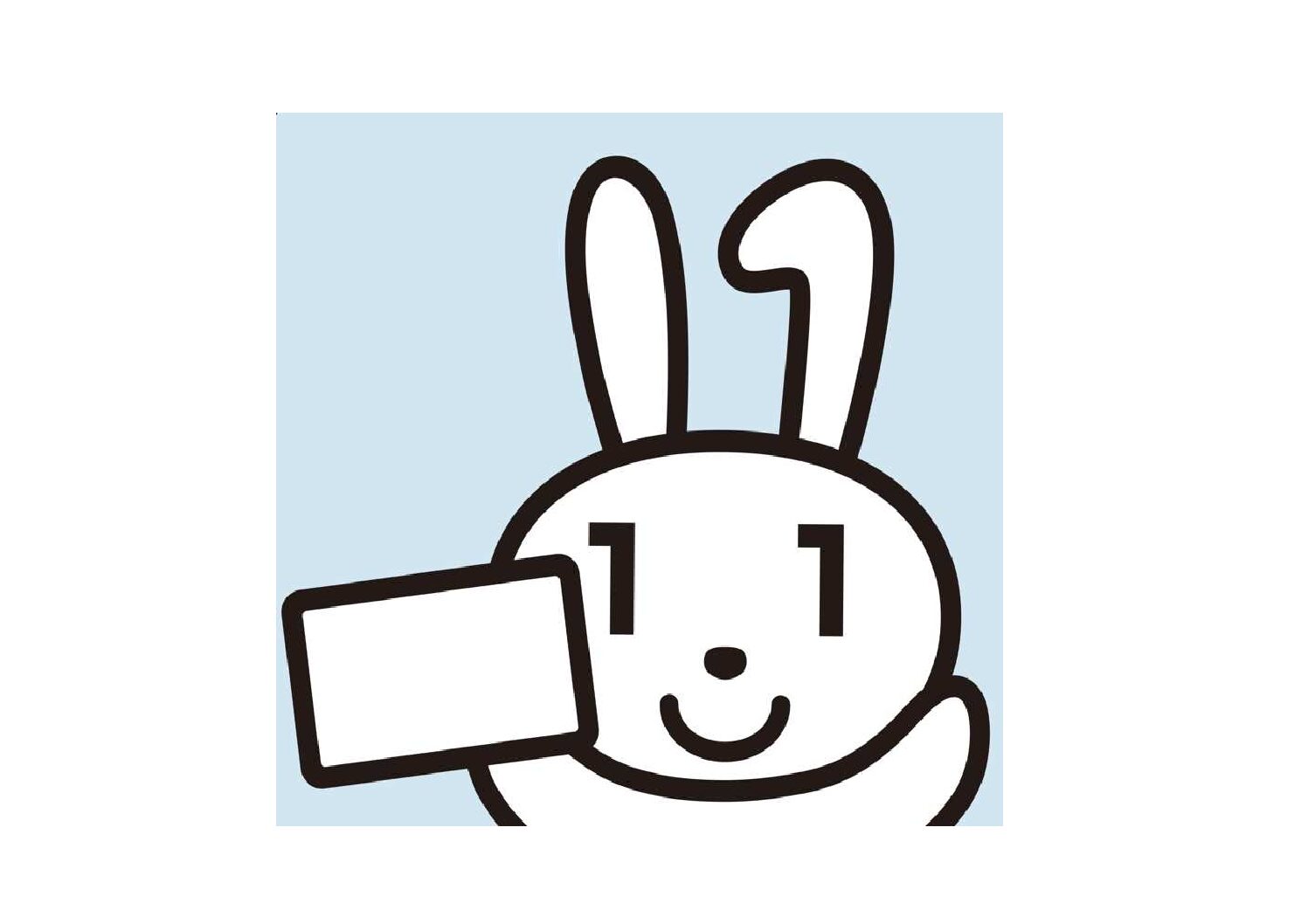- 基礎控除とは
基礎控除とは、日本の所得税・住民税に関して、納税者の所得から一定額の控除をする制度です。
令和7年度の税制改正の議論のうち、国民民主党が提案している103万円の壁の是正には、この基礎控除の改正が含まれています。
この基礎控除は、個人の最低限の生活費を保障するための制度であると考えられています。
このことは、税務大学校と呼ばれる、国税庁の職員に対して税務の教育をする機関に所属する教官が執筆した論文でも主張されています(注1)。
田中氏の論文の中で憲法25条の生存権の保障が理論的根拠であることが述べられています(注2)。
また、例えば1965年に基礎控除の引き上げがなされた際には、物価の上昇に伴って引き上げを検討したことが国会会議録に残っています(注3)。
今回のブログでは103万円の壁を題材として、税法の専門家としてどのような検討をするのか、
まとめてみたいと思います。 - 基礎控除の改正の歴史
基礎免除は、物価の上昇に伴って引き上げがなされてきていたところ、
1995年に38万円に引き上げられて以降、15年間変更がありませんでした。
ようやく2020年に38万円から48万円に引き上げられました。
ただし、給与所得控除(給与収入から自動計算で控除する制度)の制定額が10万円引き下げられたので、
いわゆる103万円の壁は変わりませんでした。
調べられた限りの基礎控除の歴史は下記のとおりです。
1947年 4,800円(基礎控除創設)
1948年 10,325円
1950年 25,000円
1953年 60,000円
1954年 67,500円
1955年 75,000円
1957年 87,500円
1958年 90,000円
1962年 100,000円
1963年 110,000円
1964年 120,000円
1965年 127,500円
1966年 140,000円
1967年 150,000円
1968年 160,000円
1969年 170,000円
1970年 180,000円
1971年 200,000円
1973年 210,000円
1974年 240,000円
1975年 260,000円
1977年 290,000円
1983年 300,000円
1984年 330,000円
1989年 350,000円(消費税3%導入時)
1995年 380,000円(消費税率5%へ引き上げに先駆けて)
2014年 380,000円(消費税率8%へ引き上げだが変わらず)
2018年 380,000円(消費税率10%へ、食品と新聞以外引き上げだが変わらず)
2020年 480,000円(15年ぶりの改正。ただし給与所得控除10万円引き下げのため103万円の壁は変わらず)
- 今後の改正の動向
自民党が令和6年12月に公表した令和7年度税制改正大綱では、基礎控除を10万円増額、給与所得控除を10万円増額、
合計20万円を引き上げて123万円をボーダー戦とする案となっています(注4)。
しかし、国民民主党は1月時点では123万円で合意をしていないため、今後どのような議論がなされるか、
注目していくこととなります。
1989年から約30年経過した2022年時点で、物価の上昇率は消費税率の引き上げも含めて約20%程度のようです(注5)。
2022年から2024年にかけても物価は上がっていたので、今までの改正の背景、歴史とそれまでの会議録を踏まえれば、
123万円以上の検討は必要となるようになるように考えられます。
一方で178万円については、国民民主党は最低賃金の上昇率を踏まえた主張です。
そうであるとすると、物価の上昇率に関しては生存権の保障のために基礎控除では検討すべきであり、
最低賃金の上昇に関する部分は基礎控除以外の制度で議論すべきなのかもしれません。
まとめ
その歴史や背景を知ることで、税制に対する理解を深めることができます。税務調査の場面でも制度背景や趣旨を踏まえて、
論理的に議論を交わして、適法か違法か、進めていくこととなります。
歴史や背景、沿革は知っておくと後々役立ちますので、改正の背景をしっかり追うようにすべきと考えています。
注1 田中康男『所得控除の今日的意義―人的控除のあり方を中心として―』(税務大学校、2004、40頁)。
注2 田中・前掲注1、40頁。
注3 参議院『第48回国会衆議院大蔵委員会会議録』第20号 (1965年3月30日)。
注4 記事執筆時点。1月24日の報道によれば150万円に引き上げる案が浮上している。
注5 日本生命 「新社会のための経済学コラム」『第154回日本の物価は35年前と比べて約2割上昇したが、世界に比べると・・・』https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/154.html 2025年1月17日閲覧。
※具体的な事案に対して適用する場合は、顧問税理士等にご相談ください。
この記事を参考にした結果発生した損害について、筆者及び当社は責任を負いかねますのでご理解のほどお願いいたします。
※2024年4月1日時点の法令等に基づいて執筆していますのでご留意ください。
※特定の政党を支持するものではありません。また法律の背景から検討したものであり、経済政策や財政などを加味したものではありません。