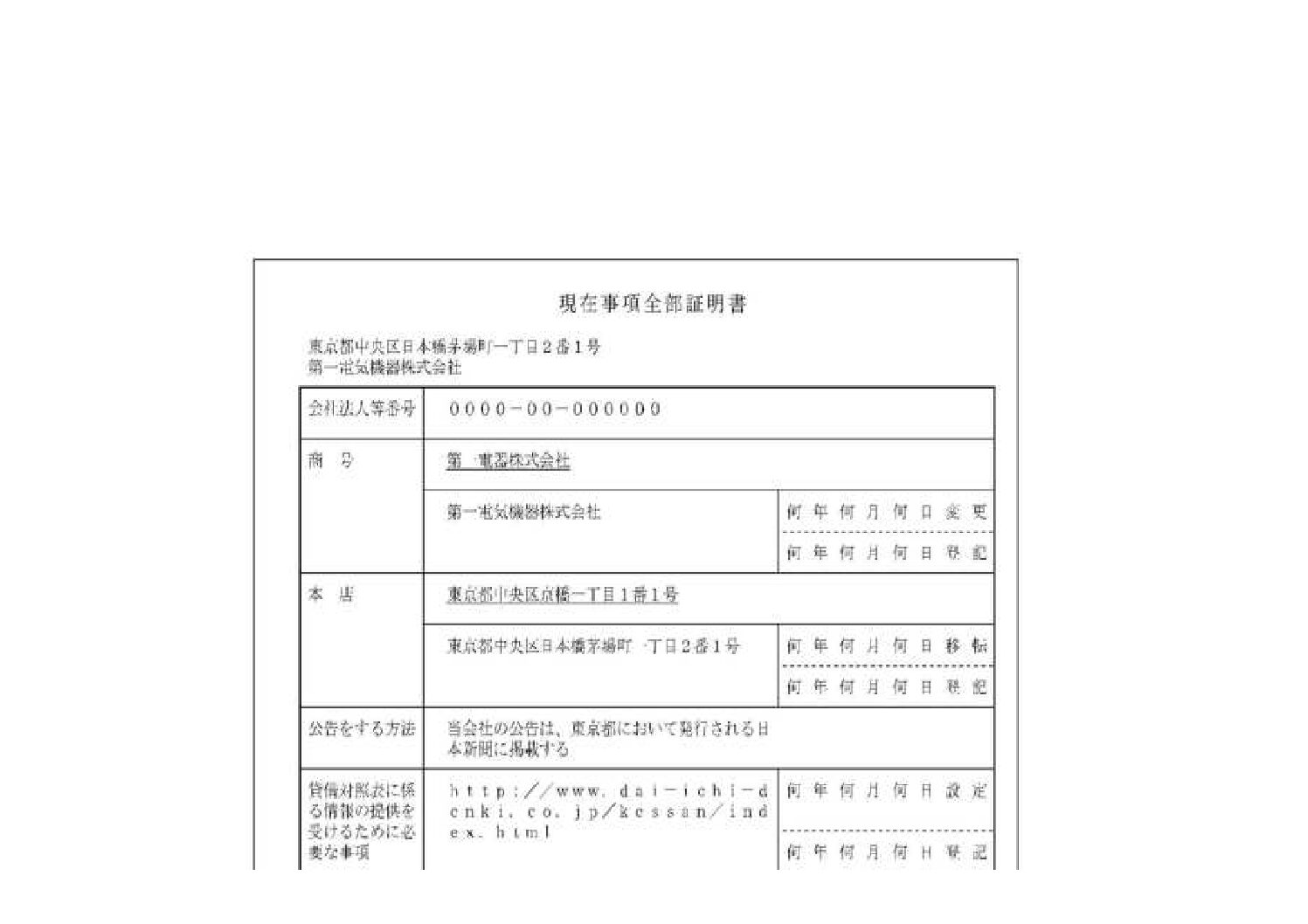1.給与所得の定義と103万円の壁
給与所得とは、雇用主から支払われる給与や賞与など、
働くことで得られる収入から給与所得控除を差し引いた後の金額を指します。
基本的には雇用契約に基づく収入は給与所得となります。
令和7年1月現在、103万円の壁をどれくらい引き上げるか、
与党と国民民主党との間で議論がなされていますが、
103万円の内訳は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を指します。
これに対して与党が12月に公表した令和7年度税制改正大綱では、
基礎控除58万円、給与所得控除65万円、合計123万円とする案となっています(注1)。
基礎控除については「103万円の壁①~基礎控除~」でまとめましたので、
本記事では給与所得控除について考えてみたいと思います。
2.給与所得控除の定義
所得、という用語は、簡単に言い換えると利益を指します。つまり、収入から経費を控除した後の金額です。
給与所得でいう必要経費は、例えば制服代、旅費、自己負担の社内飲食費、資格取得費などが考えられます。
しかし、給与所得者は非常に多いため、
国税庁側が実費による給与所得の計算による業務負荷に耐えられないこと、
給与所得者に使用させるPCなどの備品は通常、雇用主が負担していることなどから、
実費による経費控除ではなく、
概算による経費控除とすることと、所得税法で定められています(注2)。
一方、フリーランスなどの事業所得者は実額による経費控除しか認められていませんので、
実際の税負担率は異なっていることが現状です。
この不均衡については有名な裁判例があるのですが、結論としては国税側が勝訴しています。
その内容としては、給与所得者が非常に多い現状において税務行政を円滑に執行するためには、
給与所得について概算控除を適用することは妥当であるというものでした(注3)。
整理しますと、給与所得控除は、
実費による経費控除が税務行政上困難であるから、
便宜上、概算控除としている制度といえます。
3.給与所得控除の改正の歴史
給与所得控除については前述の裁判例をきっかけとして、概算控除を原則としつつも、
実費が多額に上った人については実費による経費控除も一定金額までは認める、という改正がなされました(注4)。
しかしこれは、実額控除か概算控除か、という議論の結果であり、最低賃金の上昇に基づくものではありません。
また、概算控除の金額そのものも少しずつ増額されてきましたが、
最低賃金の上昇というより、物価の上昇による議論が多かったようです。
まとめ
本記事で給与所得控除についてまとめてみたところ、
あくまで実額控除か概算控除かで制度設計されていることが分かりました。
そうであるとすると、103万円の壁を引き上げるために給与所得控除を引き上げるには、
給与所得者が一般に負担していると想定される物品の物価上昇率によるべきともいえそうです。
国民民主党が主張する178万円に引き上げるためには従来の給与所得控除の枠組みではなく、
別の枠組み、例えば最低賃金上昇率控除といった
今までにない制度を設けて給与所得控除の計算式に加える必要があるのかもしれません。
最低賃金の引き上げにより学生や主婦の「働き控え」を緩和させたい、という国民民主党の政策は、
給与所得控除や基礎控除の従来の枠組みでは対応できないので新制度を立案する必要があるように思います。
注1 記事執筆時点。1月24日の報道によれば150万円に引き上げる案が浮上している。
注2 日本税理士連合会税制審議会『給与所得課税のあり方について―平成13年度諮問に対する答申―』(2002、6頁)。
注3 最判昭和60年3月27日 民集39巻2号247頁。いわゆる大島訴訟。
注4 いわゆる特定支出控除。
※具体的な事案に対して適用する場合は、顧問税理士等にご相談ください。
この記事を参考にした結果発生した損害について、筆者及び当社は責任を負いかねますのでご理解のほどお願いいたします。
※2024年4月1日時点の法令等に基づいて執筆していますのでご留意ください。
※特定の政党を支持するものではありません。また、法律の背景から検討したものであり、経済政策や財政などを加味したものではありません。